2026年春から新一年生になる娘を持つ母として、今まさに「就職活動」をしながら考えているのが小1の壁です。保育園時代は延長保育や園のサポートに助けられてきましたが、小学校に上がると環境は一変します。授業が早く終わる、長期休暇がある、学童の定員問題など、仕事と家庭の両立に試練が待っています。

小1の壁とは?
「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学するにあたり、保護者が直面する『仕事と子育ての両立の難しさ』のことを指します。
学校は午後2〜3時に授業が終わり、学童も夕方までしか対応してくれないことが多いです。また、夏休み・冬休み・春休みといった長期休暇もあり、子どもを預ける場所の確保が課題になります。
さらに、小学生になると宿題や提出物の管理があり、子どもが「一人でできる」までにはまだまだサポートが必要です。看護師の仕事はシフト制や夜勤もあるため、特に勤務時間の調整とサポート体制が重要になります。

学童保育にも定員や利用時間に制限があります。通っている小学校に併設されている場合は見学に行ったり、場合によっては民間の学童保育も視野にいれて選ぶ必要があります。空き状況も確認しておくと安心です!
就活中に考慮すべき5つのポイント
① 勤務時間の柔軟さ
まず最優先は勤務時間です。日勤のみ、残業なし、時短勤務が可能な職場を選ぶことが大切です。小学校は保育園と違い延長保育がいため、学童の終了時間(17〜18時)に間に合う働き方を前提に探しましょう。

私の場合、長男は小学3年生ですが、学童保育を利用していないので4時間授業の日は14時半ごろの帰宅になります。特別日課の日は、幼稚園より帰宅が早いこともあります!母のお一人様時間はたったの4時間程度!働ける時間も限られています。
② 長期休暇への対応
小学校生活の最大のハードルが長期休暇です。夏休みは40日近くあり、学童が対応できない日や時間帯もあります。祖父母に頼れるか、民間学童を利用するか、あるいは職場で長期休暇中の有休取得が可能かを確認しておきましょう。
③ 学校行事・PTA対応
授業参観、運動会、懇談会など、学校行事は平日開催がほとんどです。職場が行事参加に理解を示してくれるか、代休や半休を取りやすいかは大切な判断材料です。子どもの学校生活に関わる時間を確保できる職場を選びましょう。
④ 通勤距離と勤務地
通勤時間は「見えない負担」です。30分短縮できるだけで、子どもとの時間や宿題サポートの余裕が生まれます。小学校や学童から近い職場は、急な呼び出しや体調不良にも対応しやすいので安心です。
私自身、電車通勤で1時間の職場と家から自転車で10分の職場と両方経験しましたが、勤務時間が短い方が身体的にも精神的にも負担が少なかったです。
⑤ 職場の理解とサポート体制
最後に大切なのは職場の子育て理解です。ママナースが多く働く病院やクリニックでは、同じ悩みを共有できる仲間がいます。
私自身、病棟でパートナースをやっているとき、同年代のママナースにとても励まされていました。

こどもたちも同年代だったので、小学校や幼稚園の世間話をするだけでも息抜きになりました。パートの後はお互いに習い事の送迎やごはんづくりなどを頑張っていると思うと、「私も頑張ろう!」と毎日勇気づけられていました!
求人検索をしていると、「子育て支援あり」「ママナース活躍中」と求人に書かれている職場もあります。ママナースでも働きやすい職場かどうか、要チェックです!
まとめ:小1の壁を乗り越える働き方とは
小1の壁は、避けて通れないワーママの試練です。しかし、就職活動の段階で「勤務時間」「長期休暇」「学校行事」「通勤距離」「職場の理解」という5つのポイントを意識すれば、子ども優先の働き方を見つけることは可能です。
看護師という仕事は大変ですが、同時に選択肢の幅も広い職業です。フルタイムでバリバリ働く道もあれば、非常勤やパート勤務で家庭との両立を優先する働き方もあります。大切なのは、子どもの成長を見守りながら、自分らしく働ける環境を整えることだと思っています!

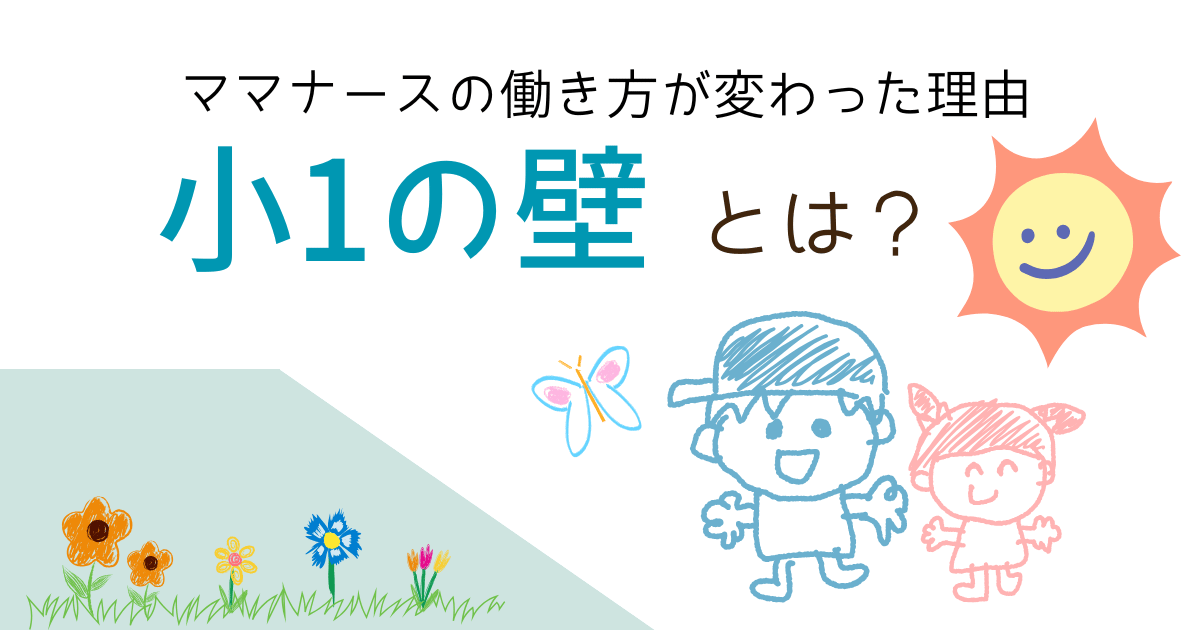
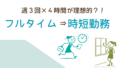

コメント