育児をしながら看護師として働く中で、
「この働き方、いつまで続けられるんだろう…」
「子どもに無理をさせていないかな…」
そんなふうに悩んだことはありませんか?
ママナースにとって、仕事と育児の両立ができるかどうかは職場選びがすべてと言っても過言ではありません。
同じ看護師の仕事でも、職場によって忙しさや働きやすさは大きく違います。
この記事では、育児中のママナースが無理なく働き続けるために知っておきたい「両立しやすい職場の特徴」を、実体験も交えながらわかりやすく解説します。
- 「今の職場を続けるか」「転職するか」を考える判断基準
- 育児と両立しやすい職場に共通する3つの特徴
- ママナースが「働きやすい」と感じやすい勤務条件の考え方
- 転職前に必ずチェックしておきたいポイント
- 無理をしすぎず、長く看護師を続けるためのヒント
ママナースが仕事と育児を両立しやすい職場の特徴【3選】
育児も、家事も、仕事も。どれも今の自分にとって大切なもの。
それでも、家事・育児・仕事をすべて両立する毎日は、想像以上に大変ですよね。
「育児と仕事、どちらも大切にしたいけれど、現実はなかなかうまくいかない…」
そんな悩みを抱えながら働いているママナースの方も多いのではないでしょうか。
しかし、看護師であっても、育児と仕事を両立しながら自分らしく働ける職場を見つけることは十分に可能です。大切なのは、職場選びのポイントを知ること。

ママナースが仕事と育児を両立しやすい職場には、共通する特徴があります。
- 残業時間が少ない
- シフトの自由度が高い
- 自分の興味のある領域を選ぶ
ここからは、ママナースが無理なく働き続けるために知っておきたい、この3つの条件について、ひとつずつ詳しく解説していきます。
残業時間が少ない
ママナースは、仕事が終わったあとに「第2の仕事」である家事や育児が待っています。
こどもたちが帰宅したら、習い事の送迎や宿題を見る時間、公園への付き添い、夕食の準備…。
「毎日どうしてこんなに忙しいの?」と思うほど、スケジュールは常にいっぱいです。

だからこそ大切なのは、こどもたちの予定に合わせて、確実に帰宅できること。
家に帰れなければ、何も始まりません!
残業のデメリット
私は約11年間、総合病院でフルタイム勤務をしてきました。途中で転職を経験し、残業の多い職場と少ない職場の両方を体験しています。いずれも病棟勤務でした。
残業の多い職場の特徴
残業が多い職場では、上司から部下まで「残業が当たり前」という雰囲気がありました。
その中で自分だけが定時で帰るのは、正直とても難しいです。
業務が立て込むと「一人だけ先に帰るのは気まずい」という空気が生まれ、結果的に自分も残業する流れに。日勤の残業は1〜2時間が当たり前で、勉強会や研修、病棟会も時間外に行われることが多く、夜勤明けや休日に出勤することもありました。
今思えばかなりハードな環境でしたが、当時は「キャリアのため」と自分を納得させて働いていました。
時短勤務のママナースもいましたが、残業になるとパパに保育園のお迎えをお願いしたり、託児所を延長したり…。
フルタイムで働くママの大変さを、身をもって感じていました。
残業の少ない職場の特徴
一方、残業の少ない職場では、日勤の残業は平均30分程度。
勉強会や研修、病棟会も勤務時間内に調整されていました。
「今日は予定があるので〇時には帰ります」と朝の時点で宣言したり、ペアで残務を調整したりと、スタッフ全体の残業に対する意識が高かったのが印象的です。
近年は、看護部の理念として残業削減を掲げる病院も増え、組織として取り組んでいる職場が増えてきていると感じます。
働きやすいのは残業のない職場
結論として、やはり残業のない職場が圧倒的に働きやすいです。
当たり前のことですが、当たり前だからこそ一番大切だと感じています。
独身の頃はキャリアアップのために多少の残業も受け入れていましたが、その働き方では疲れがたまり、家に帰ると力尽きてしまっていました。
しかし、ママは家で力尽きるわけにはいきません。
ママナースは、自分で時間を意識し、定時で帰れる働き方を選ぶことが大切です。
シフトの自由度が高い
こどもの行事や家庭の予定など、ママナースにはどうしても出勤できない日が出てきます。独身の頃と比べて、休み希望を出したり、連休の相談をしたりする機会は圧倒的に増えます。
さらに、こどもの体調不良や学校・幼稚園からの急な呼び出しなど、突発的にお休みをもらわなければならない場面も少なくありません。そんなときに、勤務日の調整をしてもらえるかどうかは、ママナースが安心して働き続けるための重要なポイントになります。
相談をしやすい環境であるか
同じように子育てを経験している同僚や上司がいる職場は、ママナースにとってとても心強い存在です。子どもの急病や学校行事に対する理解があるだけで、精神的な負担は大きく軽減されます。
私自身、月によっては小学校や幼稚園の行事が重なってしまうことがありました。上司に相談するのはとても勇気がいりますし、ほかのスタッフに休みの制限がある中で、自分だけ希望を出すことに心苦しさを感じることもありました。
それでも、「一生に一度のこどもたちのイベントには、できるだけ参加したい」「あとで後悔したくない」という思いから、思い切って相談するようにしていました。気持ちを理解してもらえる環境かどうかは、働きやすさに直結します。
制度が利用できるか確認する
ママナースは、こどものことで突発的に休まざるを得ない場面が多くあります。そんなときに活用できるのが、育児支援に関する各種制度です。
年次有給休暇:一定期間勤務した労働者に対して、賃金が支払われる休暇
子の看護休暇制度:小学3年生修了までの子どもを育てる従業員が、子どもの世話のために年間5日(子どもが2人以上の場合は10日)取得できる、年次有給休暇とは別の制度
「子の看護休暇制度」は、子どもの病気やケガ、健康診断、予防接種などの際に利用できる制度です。近年は、積極的に活用できる職場も増えています。
実際にママナースが多く在籍している職場は、育児支援制度が整い、休みを取りやすい雰囲気がある傾向があります。
転職を考える際は、有給休暇の取得状況や制度の利用実績についても、事前に確認しておくことが大切です。
自分にとって無理のないシフトで働く
ママナースにとって、急な予定変更に柔軟に対応してもらえるかどうかは非常に重要です。日勤のみ、曜日限定勤務などが可能な職場は、家庭との両立がしやすくなります。
また、パートナースの場合は、こどもの成長に合わせて勤務時間を変更できる職場もあります。家庭の状況に応じて働き方を見直せる点は、大きなメリットです。
休み希望をきちんと反映してもらえる職場は、長く安定して働くための大切な安心材料になります。転職を考える際は、シフト調整について遠慮せず、しっかり相談することをおすすめします。
自分が興味のある領域を選ぶ
3つ目は、自分が興味のある領域を選ぶことです。
ママナースが転職を考える際、どうしても家庭の事情が優先になり、勤務時間や勤務場所が限られてしまいがちです。その結果、「本当はやりたいことがあるけれど、条件を優先して別の領域を選ばざるを得ない」という状況になることも少なくありません。
しかし、せっかく看護師として働くのであれば、できるだけ自分が興味を持てる領域の仕事を選ぶことをおすすめします。なぜなら、苦手だったり興味のない分野の仕事は、長く続けるのがとてもつらくなってしまうからです。
実際、私の周りにも転職を経験している看護師はたくさんいますが、
「私はやっぱり脳外の患者さんと関わりたい」
「次も絶対にオペ室がいい」
など、それぞれ自分のやりたい領域がはっきりしていると感じます。
看護師としての経験を積めば積むほど、「これがやりたい」「これは違う」という気持ちが出てくるのは、むしろ自然なことです。
看護師として自信をもって、前向きに働き続けるためにも、自分の興味のある領域で働ける環境を選ぶことはとても重要です。

条件だけで妥協せず、「自分はどんな看護がしたいのか」を大切にしながら、ぜひいろいろな求人を見てみてください。思っている以上に、選択肢が見つかることもあります。
育児と仕事を両立しながら、自分らしく働ける職場を見つけよう
ママナースとして、育児と仕事を両立することは決して簡単ではありません。
それでも、自分に合った働き方を見つけることができれば、育児も仕事も大切にしながら、心に余裕のある毎日を送ることができます。
そのためには、まず自分がどんな働き方をしたいのか、どんな条件を大切にしたいのかを明確にすることが大切です。
無理を続けるのではなく、自分に合った環境を選ぶことで、育児もキャリアも前向きに続けていけます。
自分らしい働き方を見つけるために、ぜひ一緒に考えていきましょう。
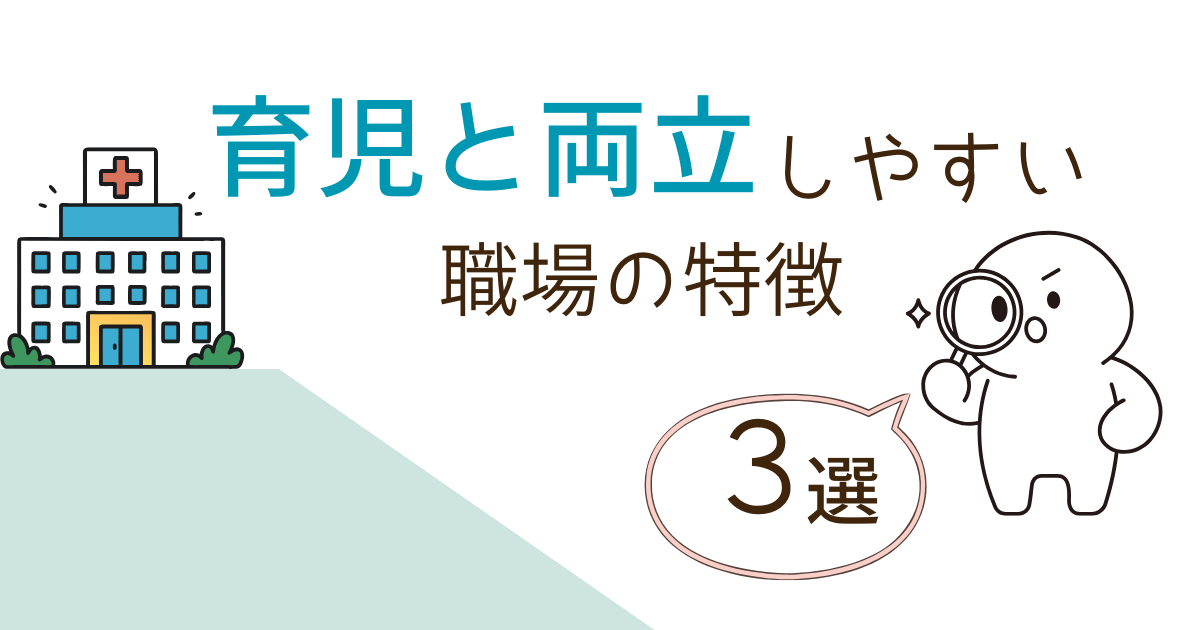
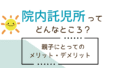
コメント