「仕事復帰したいけど、幼稚園じゃ預かり時間が短くて不安…」
「保育園との違いがよくわからないけど、幼稚園の預かり保育ってどうなの?」
そんな悩みを抱えるワーママの間で、幼稚園の預かり保育が注目を集めています。
結論から言うと、預かり保育は保育園と比べて柔軟性や費用面でメリットがある場合があり、特に条件が合えばワーママにとっても現実的な選択肢になり得ます。
私自身、2人の子どもを幼稚園に通わせているので、預かり保育を利用しながら働いていました。年々預かり保育を受ける園児の数が急増するのを目の当たりにして、改めてニーズの高さを実感しています。
この記事では、私が幼稚園の預かり保育を選ぶ7つの理由を中心に、保育園との違いや補助金制度について、利用時の注意点まで詳しく解説します。
「自分の家庭に合っているのはどっち?」と考えながら、ぜひ読んでみてください。
幼稚園の預かり保育とは?基本の仕組みと特徴

対象となる家庭
預かり保育は、以下のような家庭で利用されることが多いです。
- 共働き世帯(いわゆるワーママ・ワーパパ)
- 育児休業明けの復職予定者
- 単発的な用事(通院、家族の介護など)がある保護者
※園によっては、家庭の状況を証明する書類が必要な場合もあります。
預かり時間の例
園によって異なりますが、次のようなパターンが一般的です。
- 朝の預かり:7:30〜登園時間まで
- 夕方の預かり:保育終了後〜18:00頃まで
- 長期休暇中(夏休み・冬休みなど)にも実施される園が多いですが、施設によって異なるため事前に確認しておく必要があります。
預かり保育の費用
費用は園や自治体によって異なるため一概には言えませんが、以下のような金額帯が目安です。
| 利用時間 | 費用の目安 |
|---|---|
| 1時間ごと | 100〜300円程度 |
| 1日あたり(定額制) | 400〜1,000円程度 |
| 月額(定額制) | 5,000〜10,000円前後 |
- 長期休暇中の保育では、別料金がかかるケースもあります
- 給食やおやつ代が別途必要になることもあります
無償化と補助金の制度(満3歳〜就学前まで)
令和元年10月から実施された「幼児教育・保育の無償化」により、以下のような補助が受けられます。
- 幼稚園の教育費:月額25,700円まで無償
- 預かり保育の費用:保育の必要性が認定されれば、月額11,300円まで補助
※保護者が就労、妊娠・出産、介護などで「保育の必要性あり」と認定される必要があります。
※預かり保育の補助を受けるには、事前申請と市区町村の「保育認定(2号・新2号認定)」が必要です。
注意点
- 預かり保育の有無や時間、費用は園ごとに大きく異なります
- 園によっては、定員があり「先着順」になることもあります
- 長期休暇中は休止になる園もあるため、事前に確認が必要です
幼稚園と保育園の基本的な違い
幼稚園は文部科学省の管轄で、教育機関として位置づけられています。一方、保育園は厚生労働省の所管で、保育を主な目的とする福祉施設です。このため、幼稚園は「教育」に力を入れており、保育園は「預かる」ことに重点を置いているのが大きな違いです。預かり保育は、教育機関である幼稚園が、保護者の多様なライフスタイルに対応するために提供している柔軟なサービスといえます。
幼稚園の預かり保育を選ぶ理由7つ
柔軟な時間設定ができる
以前は短時間保育が主流だった幼稚園ですが、近年は共働き家庭の増加に対応し、預かり保育の時間帯が柔軟になっています。園によっては、早朝から夕方までの長時間保育も可能で、ライフスタイルに合わせて利用しやすくなっています。

私は週3日のパート勤務だったので、仕事のない日は通常のお迎え、仕事の日はお預かり、というように、日によって調整していました。
教育と保育をバランスよく受けられる
幼稚園本来の教育カリキュラムをベースにしつつ、預かり保育では保育的な要素も加味されており、子どもは遊びと学びをバランスよく経験できます。遊びの中にも教育的意図がある活動が組まれていることが多く、知育面でもプラスになります。
月額費用が比較的安い
認可保育園と比べ、幼稚園の預かり保育は月額費用が抑えられることがあります。保育時間が短く設定されている場合や、補助金制度を活用できる地域では、経済的な負担が軽減される点も魅力です。
補助金の対象になるケースがある
就労している保護者が対象であれば、「子育てのための施設等利用給付(無償化制度)」をはじめとする補助金が適用されることがあります。労働時間の条件を満たせば、預かり保育の費用も助成されるため、実質負担を大幅に抑えることができます。
同じ園内で一貫して過ごせる安心感
朝の登園から夕方の迎えまで、子どもが慣れ親しんだ環境で一日を過ごせる点は大きなメリットです。担任の先生や顔なじみの友達と一緒にいられることで、子どもの精神的な安定にもつながります。

うちの子は、延長保育を利用しながら園で行われている体育教室や書き方教室に通っていました。放課後に習い事ができる幼稚園が増えてきています!
空きが見つかりやすい地域もある
都市部では保育園の激戦が続く中、幼稚園の預かり保育は比較的空きが見つかりやすい地域もあります。待機児童問題の解消策として幼稚園が選ばれるケースも増えており、選択肢の一つとして検討する価値があります。
行事やカリキュラムが充実している
幼稚園は教育機関として、季節ごとの行事や体験学習が充実しています。預かり保育でも、その延長として豊かな経験ができるのが特徴です。子どもにとって楽しく充実した毎日を送れる環境が整っています。

幼稚園は、保育園や託児所に比べて園外保育や行事が多いので、様々なイベントを経験できます。親子のイベントは事前に把握して、休み希望をとるようにしました。
保育園との違いを比較|ワーママにとっての選び方
開園時間や延長保育の違い
保育園は朝7時から夜19時頃まで開園しているのが一般的で、延長保育にも対応しています。対して幼稚園は、通常保育時間が短いため、預かり保育を利用する必要があります。預かり時間も園によって異なるため、事前に確認することが必要です。
保育理念と教育内容の違い
保育園は「保育を必要とする子ども」を対象とし、生活習慣や社会性を育てることを目的としています。一方、幼稚園は「教育の場」として、文字・数・集団行動など、就学前の教育を重視しています。預かり保育では、教育の時間帯を確保したうえで、保育的な時間も持つという両面を兼ね備えています。
共働き家庭に向いているのはどちら?
共働き世帯にとって、保育時間の長さは大きなポイントです。一般的には保育園のほうが向いているとされますが、通勤時間やサポート体制などの条件が合えば、幼稚園の預かり保育でも十分に対応可能です。保護者の働き方や家庭の状況に応じて選ぶことが大切です。
幼稚園の預かり保育が合う家庭とは
勤務時間が比較的安定していたり、祖父母のサポートが得られる家庭にとって、幼稚園の預かり保育はコストパフォーマンスが高い選択肢になります。また、教育に力を入れたい家庭や、保育園の空きがない家庭にも向いています。

①自分のお子様にどのように過ごしてほしいか
②親子で無理をせずに続けられるか
という視点で、預け先を選ぶことが大切です。
幼稚園の預かり保育に関する補助金制度
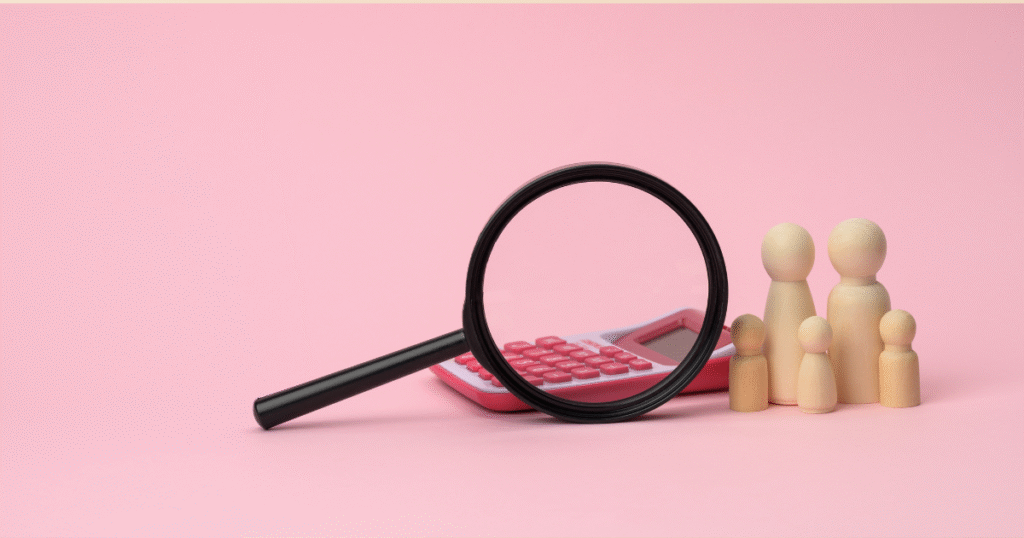
補助金制度はある?――結論:あります!
2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、幼稚園に通う満3歳~5歳の子どもを対象に、次のような補助金制度が利用できます。
- 満3歳~5歳児が対象
- 「保育の必要性」が認められれば、月額11,300円まで補助
- 自治体ごとに条件や金額が異なるため、事前確認が必須
補助金の内容と上限額
教育費:月額25,700円まで無償
これは通常の保育時間にかかる費用(入園料や保育料)を軽減するための制度です。私立・公立問わず、対象の幼稚園であれば自動的に適用されます。
預かり保育費:月額11,300円まで補助(上限あり)
預かり保育の延長時間にかかる料金に対して、月額最大11,300円まで補助されます(1日450円まで、月250時間が上限)。
ただし、これは誰でも対象になるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
補助金を受け取るための条件
「保育の必要性」の認定が必要
この補助金は、自治体が発行する「施設等利用給付認定(新2号認定)」を受けている家庭が対象です。
認定されるには、以下のような保育の必要性があることが求められます。
- 共働き(地域によって60~65時間/月と労働時間の基準は異なります。)
- 妊娠・出産
- 病気・介護
- 災害復旧活動 など
※保護者が家庭で保育できない理由があることが前提になります。
手続きの流れ
補助金を受け取るには、次のような手順が必要です。
- 市区町村の役所で「施設等利用給付認定(新2号)」を申請
- 就労証明書や申請書を提出し、認定を受ける
- 認定後、対象の預かり保育を利用
- 補助金を受け取る(※自治体によっては後払い、または請求から控除される形式)
※一部の自治体では、園を通じて申請する場合もあります。
自治体によって支援内容が異なるため注意
預かり保育に関する補助制度は、基本的な仕組みは全国共通ですが、運用方法や助成の上限額、申請書類の内容などは自治体によって異なります。
例えば:
- 月額補助の上限が独自に引き上げられている
- 長期休暇中の預かりにも補助が出る
- 利用料の立替が不要な園もある
こうした違いがあるため、必ずお住まいの市区町村の公式サイトや子育て支援窓口で最新情報を確認することが重要です。
幼稚園の預かり保育は、働く家庭にとって非常に便利な制度です。そして、条件を満たせば補助金によって費用負担を大幅に軽減することが可能です。預かり保育を検討している方は、まずはお住まいの自治体の情報を調べ、補助金を賢く活用してみてください。
幼稚園の預かり保育を選ぶ際の注意点
各幼稚園によるサービス内容の差
預かり保育の実施内容は幼稚園によって大きく異なります。時間、料金、対応内容などの違いについては、事前に説明会や見学を通じてしっかり確認しましょう。
長時間保育に向いていないケース
預かり保育はあくまで「延長保育」であり、保育園のような長時間対応を前提としていない幼稚園もあります。特に夕方以降の受け入れ態勢が整っていない場合、長時間勤務の保護者には不向きなこともあります。ママの労働状況によって、無理のない選択をすることが大事です。
夏休みや長期休暇中の対応状況
長期休暇中の預かり保育についても確認しておく必要があります。共働き家庭にとっては、夏休みや冬休み中の保育が確保できるかは大きな判断材料となるため、事前確認が欠かせません。
幼稚園の預かり保育はワーママに最適?結論と選び方のポイント
ライフスタイルに合わせた選び方
幼稚園の預かり保育は、家庭のライフスタイルにマッチすれば非常に便利な選択肢となります。子どもの成長や教育面を重視しつつ、働き方に柔軟に対応できるかを基準に判断するとよいでしょう。
見学・相談時に確認すべきチェックリスト
具体的な運用状況を質問しておくことが大切です。
資料だけではわからない情報を得る良い機会なので、必ず説明会・見学会は参加することをおすすめします。
家庭の優先事項に合わせた判断を
保護者の勤務形態や家庭のサポート体制、教育方針などを総合的に考慮し、今の自分とお子様にとって、幼稚園の預かり保育と保育園のどちらが合っているかを見極めることが必要です。あなたの家庭にとっての「最適な方法」を考えてみてくださいね。
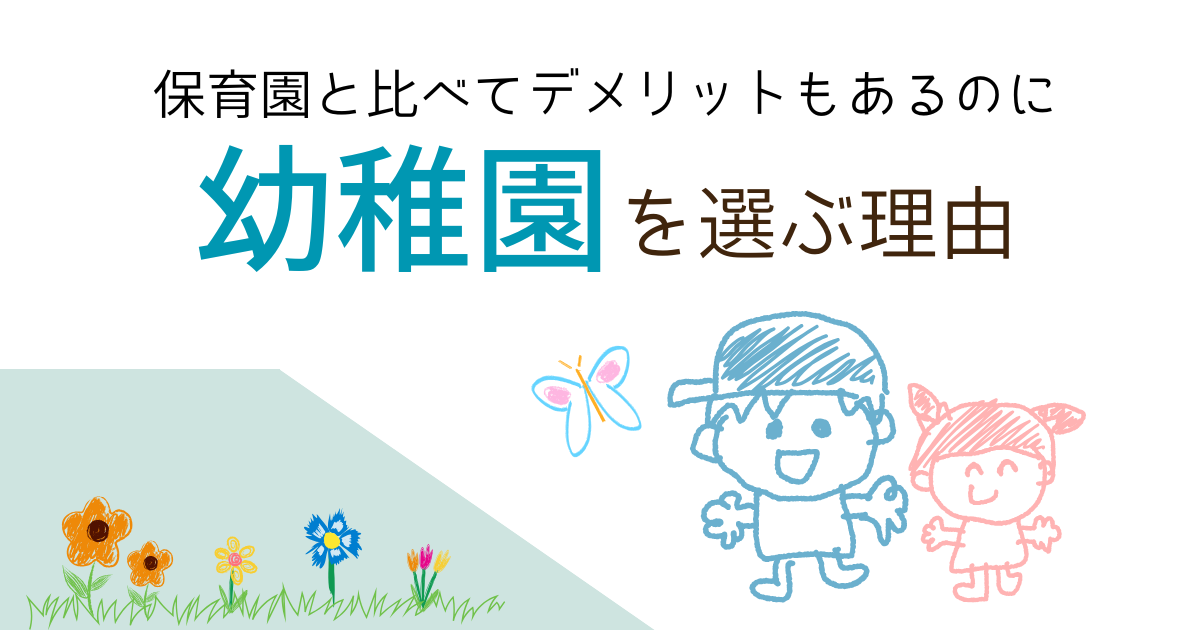
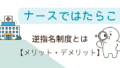

コメント